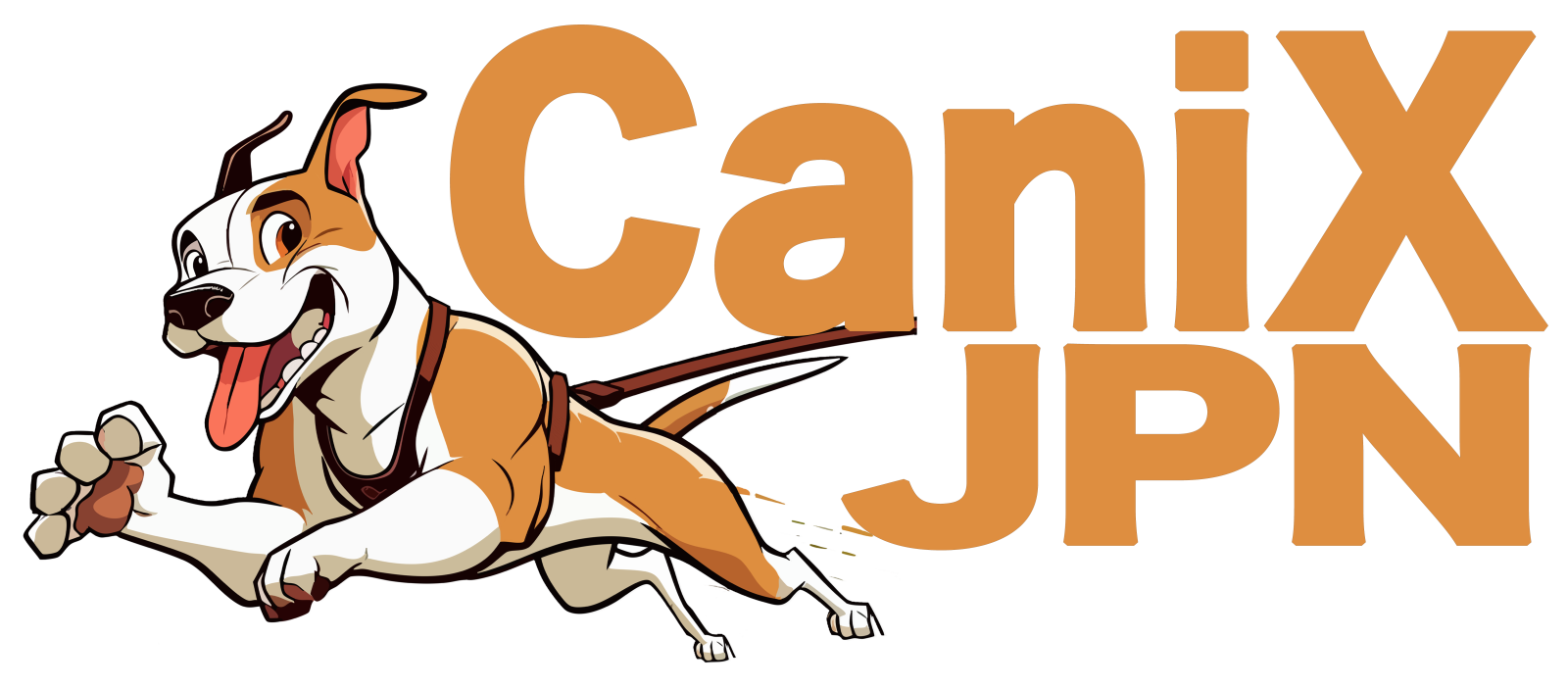ドッグスポーツ「バイクジョアリング」とは?魅力・始め方・装備を完全ガイド
バイクジョアリングは、愛犬と一緒に自転車で走る欧米発祥のドッグスポーツです。近年、日本でもアウトドア志向の高まりとともに注目されています。本記事では、バイクジョアリングの魅力から始め方、適した犬種、必要な装備、安全な練習法、コマンドトレーニング、国内外の大会情報まで、初心者でも安心して取り組めるよう網羅的に解説。愛犬との絆を深めながら、健康的なライフスタイルを築くヒントをお届けします。
バイクジョアリングの基本知識
バイクジョアリングとは?起源と語源
バイクジョアリングとは、犬と人が協力して一緒に走るスポーツの一つで、特に自転車を用いる点が特徴です。英語では「Bikejoring」と表記され、「Bike(自転車)」と「Joring(引っ張る)」を組み合わせた造語です。
このスポーツはもともと北欧、特にノルウェーを中心に犬ぞりのオフシーズントレーニングとして生まれました。雪がない季節に犬たちが力を発揮できる方法として、自転車やスクーターを使って行われるようになったのが始まりです。
バイクジョアリングでは、犬が前方に立ち、自転車に装着された専用のリードを引っ張りながら走行します。スピード感とスリルを味わえると同時に、犬との信頼関係が強く求められるスポーツです。
カニクロスや他のドッグスポーツとの違い
バイクジョアリングとよく比較されるのが、「カニクロス(Canicross)」です。カニクロスは、飼い主が自ら走りながら犬と並走・牽引するドッグスポーツで、バイクジョアリングのような自転車を使用しない点が大きな違いです。
また、スキーを使う「スキージョアリング」や、スクーターを使う「ドッグスクーター」などもありますが、バイクジョアリングはその中でもスピードが出やすく、体力とテクニックの両方が求められる競技です。
こうした類似スポーツと比較しても、バイクジョアリングは犬と人の一体感やコミュニケーション力が非常に重要であり、他のどの競技よりも密接な関係性が求められます。
さらに「カニクロス」の詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください
カニクロス完全ガイド|愛犬と始める新しいドッグスポーツの世界
なぜ今注目されているのか?人気の理由
バイクジョアリングが注目されている理由はいくつかあります。
- 犬とのコミュニケーションが深まる
- アウトドアスポーツとして健康維持に役立つ
- 比較的少ない道具で始められる
- 自然の中で楽しめる開放感がある
特にコロナ禍以降、密を避けたレジャーや自然と触れ合う機会を求める人が増加し、犬とのアクティビティとして理想的な選択肢として注目されてきました。さらに、SNSなどでの共有や、国内大会の開催増加も後押しとなっています。
さらに「ドッグスポーツ」の詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください
バイクジョアリングの魅力と体験価値
愛犬との絆が深まるスポーツ
バイクジョアリング最大の魅力は、なんといっても「犬との信頼関係の構築」です。走る中でのスピード感、アイコンタクト、音声コマンドへの反応など、あらゆる瞬間がコミュニケーションとなります。
一緒に風を切って走る感覚は、日常の散歩では味わえない絆を育みます。お互いの息が合ったときの達成感は格別で、愛犬も飼い主も自然と笑顔になります。
ストレス解消と心身の健康づくり
日頃の運動不足を解消する手段としても、バイクジョアリングは非常に効果的です。犬にとっても飼い主にとっても、有酸素運動や筋力トレーニングの役割を果たします。
また、適度な運動は犬のストレス軽減、問題行動の予防にもつながります。エネルギーをしっかりと発散させることで、より穏やかで集中力のある犬に育っていきます。
自然の中で冒険できるアウトドア性
バイクジョアリングの醍醐味は、自然との一体感です。林道や河川敷、キャンプ場など、舗装されていないオフロードでの走行は、冒険心をくすぐります。
日常とは違う風景の中を、愛犬と一緒に駆け抜ける体験は、アウトドア愛好家にとっても魅力的です。四季折々の自然を感じながら走ることで、心も体もリフレッシュできます。

どんな犬が向いている?適正犬種と条件
推奨される体格や犬種とは
バイクジョアリングは基本的に中型犬〜大型犬に適したスポーツです。目安としては体重15kg以上の犬で、筋力と持久力をある程度兼ね備えていることが推奨されます。
特に向いている犬種としては、以下のようなアクティブで走ることを好む犬たちが挙げられます:
✅シベリアンハスキー
✅アラスカンマラミュート
✅ボーダーコリー
✅ラブラドールレトリーバー
✅ジャーマンショートヘアードポインター
これらの犬種は、もともと作業犬としての素質があり、引っ張る動作やスピード走行を得意としています。特にヨーロッパでは、ポインター系の犬が大会で活躍する例が多く見られます。
小型犬でも楽しめる工夫とは?
「うちの犬は小型犬だから無理かな……」と考える飼い主の方も多いかもしれません。しかし、小型犬でもバイクジョアリングを楽しむことは十分可能です。
ポイントは「引っ張らせること」よりも「一緒に走ること」を目的にすることです。体重の軽い犬は、当然ながら引っ張る力が弱いため、飼い主のペダリングがメインになります。そのため、スピードを控えめにし、あくまで犬のペースに合わせて走ることが大切です。
また、ハーネスやリードも小型犬向けにフィットする製品を選ぶことで、快適で安全な走行が実現できます。特に、ジャックラッセルテリアやキャバリア、ミニチュアシュナウザーなど、小型ながら活発な犬種は十分に対応可能です。
犬の個性と向き合う姿勢が大切
バイクジョアリングを楽しむうえで最も重要なのは、犬の個性を尊重することです。走ることが好きな犬もいれば、のんびりとした散歩を好む犬もいます。無理に引っ張らせたり、過剰にトレーニングすることは、犬にとって大きなストレスとなります。
まずは愛犬の性格や運動習慣をよく観察し、バイクジョアリングに向いているかを見極めましょう。また、年齢や健康状態によっても向き・不向きは変わってきます。獣医師と相談しながら、無理のない範囲で始めることが理想的です。
「一緒に楽しむこと」がこのスポーツの最大の目的ですので、愛犬の表情や体調に気を配りながら、少しずつステップアップしていく姿勢が大切です。
必要な装備と安全のための準備
基本の3点セット:ハーネス・バンジーリード・アンテナ
バイクジョアリングを始めるにあたり、最初に揃えるべき装備が「3点セット」です。これが安全で快適な走行の基本となります。
✅ハーネス:犬の体に負担をかけず、引っ張りやすい形状の専用ハーネス。プリングタイプと呼ばれる引っ張り用のデザインが推奨されます。
✅バンジーリード:衝撃吸収機能を持つ伸縮性のあるリード。急な引っ張りや衝突の際のダメージを和らげてくれます。
✅バイクアンテナ:リードが前輪に絡まないようにするための補助器具。バイクのハンドルに装着し、リードの方向を一定に保ちます。
これらの装備は、犬にも人にも安全に配慮した設計がなされており、特にバイクアンテナは転倒リスクの軽減にもつながります。
安全に楽しむためのバイクと人の装備
バイクジョアリングには、特別なバイクが必要というわけではありませんが、安全性を重視するなら以下の点に注意してバイクを選びましょう。
✅頑丈なフレーム(マウンテンバイク推奨)
✅ブレーキ性能が高い(前後ディスクブレーキが理想)
✅タイヤのグリップ力がある(オフロード対応)
また、飼い主自身の装備も重要です。ヘルメットは必須であり、手袋や膝・肘のプロテクターも事故防止に役立ちます。犬の安全だけでなく、自分の身を守る意識も忘れてはなりません。
装備のメンテナンスとチェックポイント
バイクジョアリングでは、装備のメンテナンスが安全性と直結します。特に以下の項目は定期的にチェックしましょう。
✅リードの摩耗や裂け目
✅ハーネスのフィット感と変形
✅バイクアンテナの取り付け状態
✅バイク本体のブレーキやチェーンの状態
特にリードとハーネスは、毎回使用前に確認する習慣をつけることで、事故を未然に防ぐことができます。小さなほつれでも引っ張り中に破損する恐れがありますので、異常が見られたら早めに交換しましょう。
走り方のスタイルとトレーニング
クラシックな「プルモード」について
バイクジョアリングの伝統的なスタイルとして広く知られているのが「プルモード」です。これは、犬が自転車の前方でリードを張った状態で走行し、引っ張る力で飼い主をアシストするスタイルです。
特に体力のある中型犬や大型犬に適しており、犬が本来持つ走る力やスピード感を活かすことができます。犬ぞりにルーツを持つこのスタイルは、犬にとってもやりがいがあり、飼い主との一体感が生まれやすいのが魅力です。
ただし、引っ張る負担が犬に偏りすぎると疲労や関節への負担が増すため、走行中は飼い主の適度なペダリングによるサポートが重要です。犬任せにせず、「一緒に走る」という意識を持ちましょう。
近年主流の「ヒールポジション」とは
近年増えてきているのが「ヒールポジション」と呼ばれるスタイルです。これは犬が飼い主の隣を並走するようなスタイルで、引っ張る動作が少ない分、スピードコントロールがしやすいのが特徴です。
このモードは、小型犬や高齢犬、または引っ張る力が弱い犬に適しており、飼い主が自転車を操作する負担が増えるものの、犬への負荷を軽減できます。
また、ヒールポジションでは犬との距離が近いため、コミュニケーションが取りやすく、指示も通りやすくなります。初めてバイクジョアリングを行う場合や、訓練中の犬にもおすすめのスタイルです。
犬と人が一体となる走行のコツ
どちらのスタイルにおいても共通して重要なのは、「犬と人の一体感」です。呼吸や速度、タイミングを合わせて走ることが、安全で快適なバイクジョアリングを実現するカギとなります。
まずは短い距離から始め、走行中にリードが張りすぎないよう、一定のテンションを保ちましょう。また、急なカーブや停止時には、犬が混乱しないよう「止まれ」や「ゆっくり」などのコマンドを活用し、落ち着いて行動できるように導きます。
練習の際は、愛犬に適したスピードとペースで走り、リードを軽く張った状態を保つことを心がけてください。無理のない範囲で、少しずつ距離やスピードを伸ばしていくことが理想的です。

基本のコマンドと言葉の教え方
代表的な音声コマンド一覧
バイクジョアリングでは、音声によるコマンドが非常に重要です。走行中は犬に触れることができないため、言葉によって意思を伝える必要があります。代表的なコマンドは以下の通りです:
- Go / Hike: 走り出せ(スタート)
- Line out:用意
- Stop: 止まれ
- Left(Haw): 左に曲がれ
- Right(HGee): 右に曲がれ
- Slow: ゆっくり
- Wait: 待て(出発前の準備)
- Heel: 並走位置につけ
これらは必ずしも英語である必要はなく、自分と犬が理解しやすい合図で構いません。大切なのは、一貫性のある使い方です。毎回同じコマンドを使うことで、犬はその意味を確実に覚えるようになります。
日常でコマンドを覚えさせるコツ
コマンドのトレーニングは、日常生活の中で少しずつ行うことが効果的です。たとえば、散歩中に「止まれ」「左」「右」といった指示を意識的に使い、犬がその行動に従ったときに褒めてあげましょう。
また、室内や庭でも練習は可能です。おもちゃを使って指示に従わせる遊びを取り入れることで、犬が楽しみながらコマンドを学べるようになります。
重要なのは、犬にとって「コマンド=ポジティブな体験」であることです。叱るのではなく、できたらしっかりと褒める。この積み重ねが、信頼関係を築きながら指示の精度を高めていく秘訣です。
ご褒美と褒め方のタイミング
コマンドトレーニングにおいて、タイミングよく「ご褒美」を与えることは非常に効果的です。成功した直後、ほんの1秒以内に反応を返すことで、犬は自分の行動と褒美を関連づけて覚えることができます。
ご褒美は、おやつが一般的ですが、すぐに飲み込める小さなサイズにするのがポイントです。また、「よし!」「いい子!」といった声かけも犬にとって大きな報酬になります。
慣れてきたら、おやつを減らして褒め言葉だけでも反応するように移行していくと、実戦でもスムーズな指示が通るようになります。とにかく、「成功体験をたくさん与える」ことを意識して、楽しくトレーニングを続けていきましょう。
さらに「ドッグスポーツ コマンド」の詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください
愛犬と楽しむドッグスポーツ|フリスビーの始め方から競技・イベントまで完全ガイド
【愛犬と海で絆を深める】ドッグサーフィンの魅力と始め方完全ガイド
ドッグスポーツ「アジリティー」とは?犬との絆を深める魅力と始め方ガイド
初心者が始めるためのステップガイド
散歩から始めるプレトレーニング
バイクジョアリングをいきなり始めるのではなく、まずは散歩中の「引っ張らない」「指示を聞く」といった基礎的な動作を教えることから始めましょう。これがのちの走行中の安全にも直結します。
普段の散歩で「待て」「止まれ」「左」「右」などの簡単なコマンドを使ってみましょう。リードが張りすぎず、飼い主の隣または少し前を歩く状態を保つ練習を繰り返すことで、ジョアリングに必要な集中力と基本行動を自然に身につけることができます。
また、散歩中に突然引っ張ったり、他の犬や人に反応してしまう癖がある場合は、先にその問題行動の矯正も行っておくと安心です。
モード切り替えを道具で示す方法
日常の散歩とジョアリングのトレーニングを明確に分けるために、専用のハーネスやリードを使うのがおすすめです。たとえば、普段の散歩では通常の首輪とリード、ジョアリング時にはバンジーリードとプリングハーネスを使うことで、犬に「今日は一緒に走る日だ」と意識させることができます。
この切り替えによって、犬の集中力が高まり、走行中もテンションが高く保たれやすくなります。反対に、日常の散歩中に引っ張る癖がある犬には「この装備のときだけ引っ張ってもOK」と認識させることで、行動にメリハリが生まれます。
また、トレーニング前に一貫したルーティン(ハーネスを装着→バイク準備→合図)を作ることで、犬が自ら走るモードに切り替わるようになります。
初心者が陥りやすい落とし穴とは?
バイクジョアリングを始めたばかりの方がよく陥るのが、「犬任せに走りすぎる」ことです。たとえ犬が走りたがっていても、スピードや方向は飼い主がしっかりと制御する必要があります。
また、「長距離をいきなり走らせてしまう」ことも初心者によく見られるミスです。犬は興奮して無理をしてしまうことがあるため、最初は短距離(300〜500m程度)から始め、徐々に距離を伸ばすようにしましょう。
その他、「舗装された道路ばかりを走る」ことも、犬の肉球や関節に負担をかけるため注意が必要です。練習環境を整えることも、愛犬の安全のために非常に大切なポイントです。
安全に楽しむための環境とマナー
オフロード vs アスファルトの違い
バイクジョアリングは、原則としてオフロード、つまり「土」「芝生」「砂地」などの柔らかい地面で行うのが理想です。これにより、犬の肉球や足腰への負担を軽減し、安全に楽しむことができます。
アスファルトやコンクリートなどの硬い地面は、長時間の走行で肉球がすり減ったり、熱を持って火傷する危険があります。特に夏場は地面が非常に高温になっているため、涼しい時間帯を選んだり、短時間の走行に留めるなどの配慮が必要です。
もし舗装路で練習する場合には、走行時間を短く設定し、事前に犬の足をチェックしながら行ってください。また、ドッグブーツの着用を検討するのも一つの方法です。
事故や怪我を防ぐ環境作り
走行前に必ずチェックすべき項目として、以下のようなポイントがあります:
✅コースにガラス片や鋭利な石がないか
✅他の人や犬との接触がないか(視界の開けた場所で行う)
✅自転車のブレーキやギアが正常に作動しているか
✅リードやハーネスに破損がないか
また、練習前後には犬の肉球や関節を触って異常がないか確認し、適度なウォームアップとクールダウンも行いましょう。とくに寒暖差が大きい季節には、犬の体温調整にも気を配る必要があります。
法律上の注意点とマナー
日本国内において、バイクジョアリングに特化した法律は存在しませんが、道路交通法や動物愛護法などの関連法規に注意する必要があります。
特に注意したいのが「公道での走行」です。多くの自治体では、人や車の往来がある公道での犬の牽引行為(特に片手運転)は危険とみなされ、マナー違反、もしくは法律違反とされる可能性があります。
そのため、できるだけ私有地や管理された河川敷、公園内のオフロードコースなどを選びましょう。大会や練習会などの主催者も、コース設定にこの点を十分配慮しています。
また、周囲の人への配慮も大切です。散歩中の他の犬に配慮し、すれ違う際は減速する、コマンドで犬をコントロールできるようにしておくなど、マナーを守ることで、より多くの人に理解されやすくなります。

体験を深める:練習場所と大会参加
日本全国のおすすめコース
バイクジョアリングを安全かつ快適に行うためには、走行に適したコース選びが非常に重要です。日本には、オフロードや芝生、土道などの自然地形を活かしたコースが各地に存在します。
代表的なエリアとしては以下のような場所が挙げられます:
- 多摩川沿いの河川敷(東京都〜神奈川県)
- 北海道の林道・牧草地エリア
- 富士山周辺の林間トレイル(山梨県)
- 琵琶湖周辺の草地や自然公園(滋賀県)
これらの場所は、自然環境が整っており、車の往来が少ないため、犬も安心して走ることができます。もちろん、各地の天候や路面状況によって適性が変わるため、事前に下見や調査を行うことが理想的です。
初心者向けイベントとその魅力
最近では、初心者向けの体験イベントやミニレースが全国で開催されるようになってきました。こうしたイベントでは、以下のような利点があります。
- 専門家の指導を受けながら練習できる
- 安全に配慮された専用コースが用意されている
- 他の参加者との交流が楽しい
- 装備のレンタルや試用も可能
中でも「エントリークラス」や「体験クラス」といったカテゴリーは、初めて参加する飼い主や犬にとって最適です。距離も1km〜2km程度に設定されており、無理なくチャレンジできます。
イベントに参加することでモチベーションが高まり、同じ趣味を持つ仲間と出会えるのも魅力のひとつです。インスタグラムやFacebookなどのSNSでも、イベント情報は頻繁に発信されているため、定期的にチェックしてみましょう。
仲間との交流が広がる大会体験
本格的にバイクジョアリングを楽しむようになると、地域や全国規模の大会への参加を検討する方も増えてきます。大会では、スピードや走行テクニック、犬との連携力が問われますが、競技以上に重要なのが「楽しむ気持ち」です。
大会では、同じように犬を愛する仲間と知り合い、情報交換や交流を深めることができます。また、他の参加者の走行スタイルや装備を見ることで、自分の練習にも多くのヒントが得られます。
はじめは緊張してしまうかもしれませんが、大会スタッフやボランティアの方もフレンドリーで、初心者に対する配慮がしっかりしています。安心してチャレンジしてみましょう。
海外のバイクジョアリング事情
ヨーロッパでの選手権事情
バイクジョアリングは、ヨーロッパでは非常にポピュラーな競技として確立されています。特に北欧(ノルウェー、スウェーデン)や中東欧(チェコ、ドイツ)では、国際大会も頻繁に開催されています。
世界規模の大会では、ICF(International Canicross Federation)やIFSS(International Federation of Sleddog Sports)といった組織が主催となり、1,000人以上が参加する大規模イベントもあります。犬のスピードや反応の精度、装備の最先端性が求められる本格的な競技です。
また、現地ではプロチームやスポンサーがついている選手も多く、まさに「スポーツ」として高い認知度があります。
海外と日本の装備の違い
海外と日本では、使用される装備にも違いがあります。欧州では、機能性と耐久性を重視した装備が中心で、素材の質や快適性に優れた製品が多く流通しています。
たとえば、バイクアンテナには可動式のスプリング構造が組み込まれていたり、ハーネスには犬種ごとに微調整できるデザインが採用されていることが一般的です。
日本国内ではまだ選択肢が少ない面もありますが、海外通販や代理店経由で手に入れることも可能です。最近では国内ブランドも増えつつあり、徐々に装備環境が整ってきています。
国際ルールとそのトレンド
バイクジョアリングの国際大会では、細かなルールが定められています。例えば、犬の前方走行の義務、装備の種類、スタート方法、走行距離などが明確に規定されており、公平性と動物福祉の両立を重視しています。
また、近年のトレンドとしては、「犬のコンディション重視」「オフロード重視」「環境負荷の少ない大会運営」などが挙げられます。動物福祉に対する意識の高まりにより、無理をさせない運営方針が国際的にも求められています。

バイクジョアリングが変えるライフスタイル
運動を日常に取り入れる習慣化
バイクジョアリングを始めることで、自然と飼い主自身の生活にも良い変化が生まれます。定期的に愛犬とアウトドアで走る習慣は、飼い主の運動不足の解消にもつながります。
忙しい日々の中でも、朝や夕方に軽く走る時間を設けることで、日常にリズムが生まれ、心身ともに健やかな生活を送ることができるようになります。
さらに、ジョアリングのために愛犬の体調管理や栄養にも気を配るようになり、結果的に飼い主自身の健康意識も高まるという好循環が生まれます。
飼い主としての成長と視野の拡大
バイクジョアリングでは、犬とのコミュニケーション力や観察力が求められます。犬の状態を読み取る力や、言葉以外のサインを理解する力が自然と養われ、飼い主としてのスキルが向上していきます。
また、大会やイベントを通じて他の愛犬家と交流することで、新しい価値観や情報に触れる機会が増え、ペットとの関わり方に対する視野も広がります。これは、単なる趣味を超えて、人生そのものを豊かにする体験となるでしょう。
SNSやコミュニティでの繋がり
近年では、SNSを通じてバイクジョアリングの仲間と情報交換をしたり、走行風景を投稿することでモチベーションを維持している飼い主が増えています。
InstagramやFacebookでは、#バイクジョアリング、#ドッグスポーツ などのハッシュタグで多くの実践者の投稿を見ることができ、装備選びやトレーニングの参考になるだけでなく、全国各地のイベント情報もいち早く得ることができます。
リアルとオンラインの両方で仲間ができることで、バイクジョアリングは「一人で行う運動」から「仲間と楽しむライフスタイル」へと進化していきます。
始める前に知っておきたい注意点
犬の健康状態と事前診断
どんなに走るのが好きな犬でも、健康であることが第一条件です。特に持病がある犬、高齢犬、成長期の子犬などは、獣医師の診断を受けてからジョアリングに取り組むようにしましょう。
また、股関節や膝に不安がある犬種(特に大型犬)は、長距離の走行が負担になる可能性があるため、無理のない運動計画を立てる必要があります。
定期的な健康診断と、トレーニング中の細かな体調変化の観察は、安全に楽しむための基本です。
費用感と初期投資の目安
バイクジョアリングを始めるにあたっての初期投資は、装備の品質や種類によって変動しますが、以下が大まかな目安です:
- バンジーリード:5,000〜10,000円
- プリングハーネス:8,000〜15,000円
- バイクアンテナ:10,000〜20,000円
- ヘルメットやプロテクター:5,000〜10,000円
合計で約3〜5万円程度が目安となります。自転車をすでに所有している場合はこの費用で済みますが、バイク自体の購入が必要な場合は追加費用が発生します。
また、大会やイベントに参加する場合は、参加費や交通費も必要となるため、年間でのランニングコストも考慮に入れておきましょう。
継続するためのスケジュール設計
始めたはいいものの、継続できなければ意味がありません。週に1〜2回の練習でも、愛犬との時間を大切にしながら継続できるよう、スケジュールを立ててみましょう。
また、天候や体調によっては休む日を作るなど、柔軟に対応することも大切です。無理をせず、愛犬の「楽しい」を大切にしたスケジュールこそが、長続きの秘訣です。
まとめ:バイクジョアリングを楽しむために
“完璧”より“楽しむ姿勢”が大切
バイクジョアリングは、犬との絆を深め、健康的でアクティブなライフスタイルを楽しむためのスポーツです。速く走ることや技術を磨くことも素晴らしいことですが、何よりも「楽しい」「またやりたい」と感じる気持ちが一番大切です。
犬の笑顔が最高の成果
走り終えたあと、満足そうな表情でこちらを見つめる愛犬。その笑顔こそが、何よりのご褒美であり、成果です。バイクジョアリングは、競争や記録を追い求めるものではなく、愛犬との時間をかけがえのない思い出に変えるスポーツです。
まずは一歩、今日から始めよう!
もし興味を持ってこの記事をここまで読んでくださったのなら、それはもうスタート地点に立っているということです。まずは装備をチェックして、いつもの散歩に少しの「走り」を取り入れてみてください。それが、バイクジョアリングという素晴らしい冒険の第一歩になるはずです。

よくある質問(FAQ)
何歳から始められますか?
一般的には、犬の骨格や筋肉が発達する生後12〜18ヶ月以降が目安とされています。大型犬の場合は成長がゆっくりなため、開始時期は遅めが理想です。必ず獣医師と相談のうえ、体への負担が少ない形でスタートしましょう。
どのくらいの頻度で練習すればいい?
週に1〜2回から始めるのが無理のないペースです。犬の体力や年齢に応じて調整し、1回あたりの走行距離は1〜3km程度から徐々に伸ばしていくのが望ましいです。
犬が疲れてきたらどうする?
走行中に犬がペースを落としたり、後ろを振り返る仕草を見せたら、無理をせずに一度止まりましょう。水分補給や短い休憩を挟むことで、犬の負担を軽減できます。
初期費用はどれくらいかかる?
装備一式(ハーネス、リード、アンテナ)でおおよそ3〜5万円が目安です。必要に応じてバイクやヘルメット、プロテクターなどを追加するとさらに費用がかかります。
大会に出場するにはどうすればいい?
バイクジョアリングの大会は、各地のドッグスポーツ団体やクラブによって開催されています。公式サイトやSNS、ドッグイベント情報サイトなどで開催情報をチェックし、エントリー条件や装備基準を確認しましょう。
ドッグスペシャリストナビ運営事務局は、愛犬家の皆さまに信頼できる専門家やサービスの情報を提供しています。