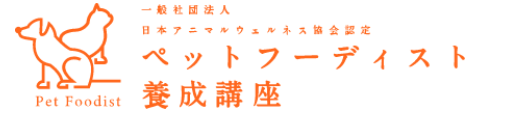“健康”とは、病気でないことだけを指すのでしょうか?
犬と暮らす私たち飼い主にとって、本当の意味での「幸せな時間」とは何か——
そんな問いに静かに向き合っているのが、日本アニマルウェルネス協会です。
今回は、同協会の事務局長・日笠さんにインタビュー。
「動物が動物らしく生きる」ことをテーマに、ホリスティックケアや食の専門知識、そして犬と心を通わせるためのヒントを伺いました。
目次
飼い主だからこそ学べる「動物との向き合い方」
――一般社団法人日本アニマルウェルネス協会の活動について教えていただけますか?
日本アニマルウェルネス協会は2009年に設立されました。ペットブームの真っただ中で、「もっとペットの健康や幸せを考える時代にしたい」との思いからスタートしました。当時は、しつけなどの情報も少なく、健康を意識したフードやケアなども限られていました。ドッグトレーナーさんなどプロの方も今と比べると少なかったです。そのため、動物たちの「心・身体・環境」などすべてを含んだ“ウェルネス”をテーマに活動したいと考え、現在にいたります。
動物福祉とウェルネス、その違いとは?
――アニマルウェルネスと動物福祉(アニマルウェルフェア)の違いについて教えていただけますか?
動物福祉は、人間による動物の利用を認めつつ、その利用をできるだけ最低限にとどめ、動物に苦痛を与えないよう配慮しようとする考え。人間の主観や感情ではなく、客観的かつ科学的に動物の幸せを考えたり、動物の生命を尊重するだけでなく、生活の質(QOL)にも配慮することです。 イギリスで提唱された「動物の5つの自由」は国際的な動物福祉の指標とされています。
🐾 動物の5つの自由(Five Freedoms)
1.飢えや渇きからの自由:Freedom from Hunger and Thirst
健康維持のために適切な食事と水を与えること。
2.痛み・負傷・病気からの自由:Freedom from Pain, Injury or Disease
ケガや病気から守り、病気の場合には充分な獣医医療を施すこと。
3.恐怖や抑圧からの自由:Freedom from Fear and Distress
過度なストレスとなる恐怖や抑圧を与えず、それらから守ること。
動物も痛みや苦痛を感じるという立場から、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担もできうる限り避けること。
4.不快からの自由:Freedom from Discomfort
温度・湿度・照度など、それぞれの動物にとって快適な環境を用意すること。
自由に身体の向きを変えることができ、自然に立つことができ、楽に横たわることができること。
炎天下の日差しや、雨や風をしのぐことができること。群れで生活する動物は、同種の仲間の存在が必要である。
身動きもできない狭い場所、糞尿にまみれた状態、日よけのない炎天下、雨や風、騒音などにさらされているといった飼育環境は、動物にとって好ましくない。
5.自然な行動をする自由:Freedom to Express Normal Behavior
各々の動物種の生態・習性に従った自然な行動が行えるようにすること。
群れで生活する動物は、同種の仲間の存在が必要である。
どれも動物にとって基本的なニーズですよね。ただ、私たちが目指すアニマルウェルネスは、その“先”も大切にしています。 たとえば、痛みがない、ストレスがないという「苦痛の回避」だけでなく、犬が本来の行動を楽しめているか、心が満たされているか、飼い主との絆が築かれているかなど。そういった“心身の幸福”の実現を目指しているのが、ウェルネスの考え方であり、 動物が“動物らしく”生きられるように、日々の暮らしの中で「幸せを増やす視点」を私たちは大切にしています。 そしてこれらを前提に、コンパニオンアニマルたちの生活の質を高める手段が、ホリスティックケアなのです。

『ペットフーディスト』と『ホリスティックケア・カウンセラー』とは?
――協会ではどのようなことが学べますか?
現在は2つの資格講座を中心に人材育成を行っています。 1つ目が「ペットフーディスト」。犬猫の基礎栄養学、消化吸収のしくみ、ペットフードの選び方や与え方、手作り食の作り方、病気の時の食事管理、介護期の食事など、食に関する幅広い知識が学べる講座です。
2つ目は「ホリスティックケア・カウンセラー」。こちらは基礎的な健康を支える食事の知識の他、犬猫の基礎知識や行動、ペットマッサージ、ハーブやアロマテラピーなどを含むケアを幅広く学びます。 どちらの講座も通信制なので、ご自身のペースで学んでいただけます。受講期間はお申し込みから最長2年間で、平均的には1年前後で修了される方が多いです。試験は期間内であれば最大3回まで受けることができます。
――受講者はどんな方が多いですか?
協会としては犬に関する仕事に役立てていただけるように、プロの方の受講を想定していますが、「愛犬のために」とお考えの熱心な飼い主さんの受講も多いです。1頭目を見送った後に、「次の子にはもっと良いケアをしてあげたい」「後悔したくない」という理由で学び始める方もいらっしゃいます。
「ごはんを食べない」「涙やけ」――日常の悩みに知識で向き合う
――受講のきっかけには、どんな悩みが多いのでしょうか?
本当にさまざまですが、最近は「食べない」というお悩みをよく聞きます。季節や体調が理由ではなく、食への興味そのものが薄い子もいます。他にも「涙やけ」や「体重管理」など、飼い主さんが直面する課題は多岐にわたります。
――プロの方向けと伺いましたが、講座の内容は初心者でも理解できますか?
大切なのは「やる気」です。知識ゼロから始めた方もたくさんいます。共通しているのは「愛犬・愛猫を想う気持ち」です。その気持ちが強い方は、忙しくてもテキストを読んだり動画を見たりして学びを深められていきますし、「久しぶりの勉強だから不安だったけど、楽しくて仕方なかった」と学ぶこと自体を楽しんでいる方もいらっしゃいます。
飼い主さんの手はいつでも愛犬の「ゴッドハンド」になる
――犬にもマッサージは良いのでしょうか?
はい、愛犬にとっても、飼い主さんにとっても、おすすめのホリスティックケアです。ペットマッサージは、母犬が子犬を舐めて免疫力を高めるのと同じように、愛情を伝えながら心身を健やかに保つための行為といえます。体表を優しくなでたり揉んだりすることは、犬にとっては心身がリラックスして落ち着き、飼い主さんにとっては愛犬との間に親子のような深い信頼関係を築くことができます。ちょっとした知識を知って、元気なうちから日々の習慣に取り入れることで、愛犬の健康維持と深い絆づくりに繋がるので、とてもおすすめです。

“できない”ではなく“できる”に目を向けるグルーミング
――実際のエピソードを教えていただけますか。
ホリスティック・グルーミングを実践しているサロンのホリスティックケア・カウンセラーによる実例なのですが、シャワーや爪切りが大嫌いで、サロンに来ることすら怖がっていたお客様(愛犬)がいました。でも、担当グルーマーは「できない」ことではなく「できる」ことに目を向けたんですね。「右足しか爪を切らせてくれなかった」ではなく、「右足は切らせてくれた」と受け止め、その子のペースで無理なく楽しいことを織り交ぜながら接したことで、少しずつ安心してくれるようになりました。最初はキャリーバッグから出てくることすらしてくれなかった子が、次第にしっぽを振ってサロンに来てくれるようになって。最終的には爪切りの時も、自ら足を差し出すようにまでなりました。
――すごい!その変化に寄り添えるのがホリスティックな考え方やホリスティックケアなのですね。
はい。「この人なら大丈夫」と感じてもらえる関係づくりが大切です。犬の気持ちに寄り添う姿勢こそが、真のプロフェッショナルだと思います。
プロとつながることで「犬との生活」がもっと豊かになる
――ドッグスペシャリストナビをご覧の読者に向けて、メッセージをお願いします。
最近は飼い主さんの意識も本当に高くなりました。その一方で、知識があるがゆえに視野が狭くなり、苦しんでしまう方や愛犬に合っていない方法を試し続けてしまっている方もいます。 でも、今はネットが普及し、ドッグスペシャリストナビや、インスタなどのSNSなど、様々な方法で信頼できるプロとつながることができます。獣医師、トリマー、トレーナー、ペットフーディスト、ホリスティックケア・カウンセラー…たくさんのプロがいますので相性が合う方を見つけて、頼ってください。「犬との生活って最高だね」と感じられるように、プロが力になります。
アニマルウェルネス協会の「動物の幸せは、単なる“健康”を超えたところにある」という理念に、深く共感しました。 とくに印象的だったのは、「今できていることに目を向ける」というグルーミングの姿勢。これは人間関係にも通じる、優しさに満ちた哲学だと感じます。そして、専門知識を持つプロを頼ったことで、恐怖を感じずにグルーミングできるようになった犬の姿に、“満たされた幸せ”を見た気がしました。 この記事が、犬との暮らしに悩んでいるすべての方にとって、プロとつながるためのきっかけになれば幸いです。
ドッグスペシャリストナビ運営事務局は、愛犬家の皆さまに信頼できる専門家やサービスの情報を提供しています。